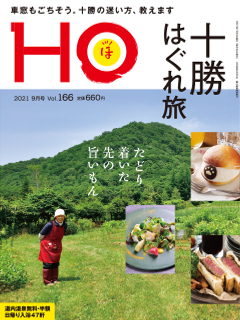街の身近な健康相談vol.36 4年半にわたり、北海道中医薬研究会の会員店の店主さんのご紹介をしてきましたこの企画は今回で一区切りとなります。北海道各地域の文化や人の活動を“温泉”を中心に独自取材で紹介されてきました北海道情報誌:HOが2025年12月号で休刊となるためです。最後のご紹介は国際中医専門員の資格をとられた室蘭の附田綾さんと国際中医専門員及び国際中医薬膳師の資格をとられた札幌の遠藤大輔さんへのインタビューです。この資格は民間の任意団体が認める資格ではありますが、専門の勉強を積み重ねないとなかなかとれない資格です。そのお二人から今回は“薬膳”をテーマにお話し頂きました。

街の身近な健康相談vol.35 体の中にはたくさんの内臓と器官があり、神経を含めた複雑なネットワークのつながりで生命活動が営まれています。中医学(中国の伝統医学)の場合、哲学的思想もあり、もう少しシンプルなとらえ方をします。それが『五臓六腑(ごぞうろっぷ)』という内臓の考え方です。五臓は「肝」「心」「脾」「肺」「腎」で5つ。六腑は「胆」「小腸」「胃」「大腸」「膀胱」「三焦」で6つ。五臓は気血水精を作り出し、貯蔵する器官であり、六腑は飲食物の消化や排泄に関わる器官と考えます。今回はこの五臓六腑の働きを大切に考える店主さんがおられるお店の紹介です。

街の身近な健康相談vol.34 私たち北海道中医薬研究会は、“中医学(中国の伝統医学)”を一緒に学びあう仲間です。2024年に釧路市に新しい仲間が増えました。「漢方薬店・漢方アロマサロン萌芽(ほうが)」さんです。以前は、救急外来部門で看護師として働いておられたとのこと。病院の中でも一番忙しい部署のため、患者さんと向き合う時間を作ることが難しかったそうです。子育てをしながら漢方を一から学び、独立してサロンを開業されたことは、とても大きな志とエネルギーを持っておられる方だと思います。

街の身近な健康相談vol.33 私たち北海道中医薬研究会は、“中医学(中国の伝統医学)”を一緒に学びあう仲間です。今年新しい仲間が増えました。小樽の老舗(1901年創業)三ツ野薬局さんです。小樽駅前アーケード:サンモール一番街を歩いている方にはなじみのお店だと思います。今回、中医学の健康相談を担当される方に季節の養生について伺いました。

街の身近な健康相談vol.32 今年は、6月中から全道各地で真夏日を観測し、暑さ厳しい夏になりそうです。また近年は“湿度が高い”夏が当たり前になってきました。高温多湿な夏に体調を崩さないよう、池田有希さんにお話しを伺いました。

街の身近な健康相談vol.31 中医学(中国の伝統医学)の知恵を日々の生活や身体のケアに役立てていただきたい。またお近くにあれば、ぜひ直接ご自身にあった方法をご相談して頂きたいとの思いで、北海道各地の中医学に詳しい方にお話しして頂くこの企画が今年で5年目を迎えました。今回は河野裕樹さんに「中医学と西洋医学の違い」についてお話しいただきました。

街の身近な健康相談vol.30 何か気になる症状がある時に検索することが一般的になっています。その際に当てはまりそうな病名やおすすめの養生法がいくつも出てきた時、どれが自分に合っているのか、そもそも受診した方がよいのか迷い、不安になってしまった体験はありませんか?そのような時に“相談できるかかりつけの店”があるとどうでしょうか?

街の身近な健康相談vol.29 「国際中医専門員」という認定資格があることをご存じの方はかなりの通です。中国の伝統医学=中医学は、中国では専門の国家資格があり、“中医師(ちゅういし)”と呼ばれます。国家資格の医師です。中国以外にも日本をはじめ世界中で中医学を学んでいる方達がいます。その方達に向けて、中国政府の外郭団体:世界中医薬学会連合会が主催している試験に合格すると認定を受けることが出来る資格が「国際中医専門員」です。今回それぞれの思いを胸に温めながら、試験に臨まれ、見事合格されましたお二人にお話を伺いました。

街の身近な健康相談vol.28 「生き生きと元気に毎日を送るコツ」を中医学(中国の伝統医学)的に考えると?について、札幌市西区『漢方薬局いちやく草』上村由美さんがお話を聞かせてくれました。難しい専門用語で「補腎(ほじん)」と「活血(かっけつ)」がキーワードとのこと。「補腎」の考え方を大事にすると、身体の成長・発育・生殖・老化を健やかに穏やかに迎えることができるそうです。「活血」の考え方を大事にすると、身体中を巡っている太い血管から細い血管、また血液まで年齢を重ねても守ることができるそうです。そして上村さんは、中医学以外にもコツがあるとのこと。それは何でしょうか?

街の身近な健康相談vol.27 「起立性調節障害」という病気をご存じでしょうか?起床時、起き上がろうとすると様々な症状が現れ、活動することが困難になる病気です。自律神経の調節がうまくいかないことが原因ですが、治療法が確立していないため、長期に続くと心理的な負担にもなり、児童生徒学生の場合は学校生活が、成人の場合は社会生活が制限されてしまう問題も併発します。札幌市北区の『カシダ天光堂』樫田美保さんは、この疾患に取り組んでおられ、お話を聞かせてくれました。

街の身近な健康相談vol.26 森林と紫蘇と海の香がする町:白糠町(しらぬか)。この町には町立病院がありません。元はありましたが、町民話し合いのもと、赤字経営になりやすい病院の維持ではない方法で町民の健康を守ることを英断した町です。その白糠町にて、親子で地域の健康を守っている薬局があります。『みま薬局』さんです。オレンジ色の馬のマークは地域の方なら知っている目印ではないかと思います。今回は二代目となった美馬雅俊さんにどのような思いで継ぎ、地域の方の健康と向き合っているかについて、お話を聞きました。

街の身近な健康相談vol.25 今年も暑すぎる夏がやってきました。梅雨はないものの、湿度も高い日が続いております。夏特有の不調の原因に、中医学では“湿邪(しつじゃ)”の影響を考えますが、そこからさらに踏み込んで「“痰湿(たんしつ)”という老廃物がたまっている方が増えています」と警鐘を鳴らして下さる方からお話を伺いました。“痰湿”とはなんでしょうか?そしてどうすると改善できるのでしょうか?
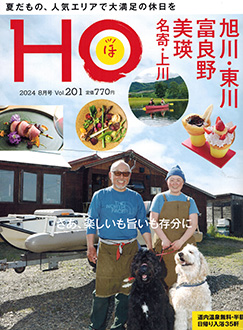
街の身近な健康相談vol.24 大変広い北海道。温暖化してきているといえども、夏は涼しいオホーツク・紋別市。地域に暮らす方で、痰がからむ咳に悩む方がおられるとのこと。なぜでしょうか?紋別市に暮らす方の健康を長年見守ってきた金子さんの観察力と中医学の知恵を結ぶお話です。
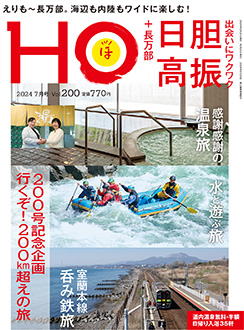
街の身近な健康相談vol.23 『中医学(ちゅういがく)』に携わっている方は誰しも、初めて『中医学』に出会った時があり、また中成薬(ちゅうせいやく)や漢方薬を服用するということを頭での理解とは別に、体感としてお持ちの方も多いと思います。今回はお二人の店主さんにインタビューしました。
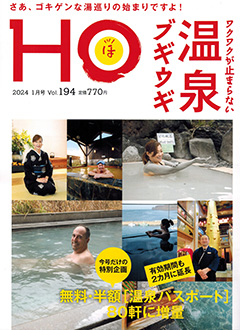
街の身近な健康相談vol.22 北海道では突然冬がやってくることがあります。今年は驚くほどでした。札幌の場合、17℃→10℃→-4℃と3日間で急激に下がり、しかも真冬日(最高気温0℃未満の日)に。街は一夜で冬景色に変わりました。ですが、今号の特集は熱い内容です。2019~2022年に薬店・薬局を開業されたお二方に漢方相談を始めた思いをインタビューしております。
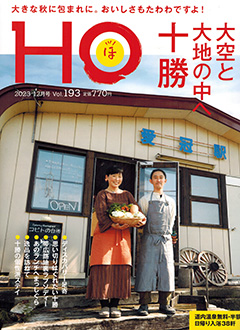
街の身近な健康相談vol.21 北海道では、冬の訪れを教えてくれる“雪虫”が飛ぶシーズンを迎えています。今年は夏の猛暑と秋の暖かさの影響で大量発生し、札幌市・小樽市では外出を控えてしまうほどです。雪虫が育つ樹木が多くある地域では、来年も気をつける必要がありそうです。冬に向けての準備は私たちにも必要です。猛暑の影響が秋に出やすいように、冬の養生は来年の春につながります。冬に守ると良い五臓は『腎(じん)』です。“腎”の働きの1つに、生殖機能の維持(性ホルモンの適切や生成と分泌)があります。男女ともに関係する働きです。また、老化に関わる内臓でもありますので、年齢を重ねても若々しくありたいと願う私たちにとって大事な内臓です。

街の身近な健康相談vol.20 朝晩と日中の気温差が大きくなってきました。寒いと感じる感覚は自分の身体の変化を見つける機会にもなります。“疲れの回復具合”“髪質や抜け毛の変化”“目の調子”などの症状もその1つです。今回は加齢によるものと済まされてしまいがちな体調について、中医学で考えるところの内臓“腎(じん)”から考えてみるお話です。

街の身近な健康相談vol.19 記録的猛暑となった北海道も、9月に入りますと朝晩は過ごしやすくなり、お出かけする機会が増えてくるかと思います。今回の身近な健康相談は、“旅の養生”についてです。旅行中も旅から戻ってきてからも役立つ中医学の知恵をご紹介します。
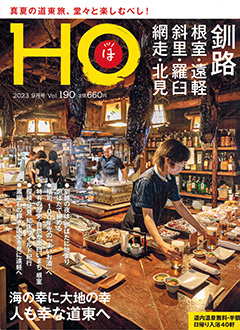
街の身近な健康相談vol.18 蒸し暑い日が続いております。特に寝苦しい夜が続きますと、食欲が落ち、体力も次第に奪われていきますので、注意が必要な季節です。体力、食欲が落ちないように夏の土用の意味を一緒に考えましょうと提案してくれている記事が今号です。実は一年に4回ある土用は季節の変わり目の時期と考えます。夏の土用は『脾(ひ)』という内臓に注目することがポイントです。ぜひご覧ください。
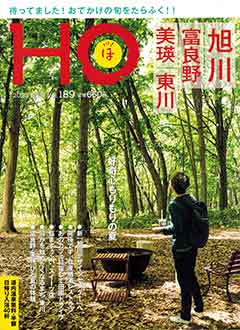
街の身近な健康相談vol.17 北海道も夏が始まりました。熱中症は暑さに慣れていない時期に起きやすい傾向があります。熱中症を防ぐために守りたい内臓の1つは心臓です。中医学で考える内臓:心(しん)には心臓の働きも含みます。そして他にも健康を守る大事な働きを持つと考えます。今回取り上げているテーマは『心臓とこころを司る「心」』です。ご覧ください。
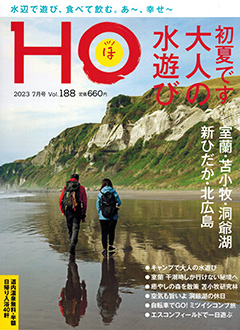
街の身近な健康相談vol.16 気温の変動が激しい時期は季節の変わり目です。この時期に気をつけてもらいたい内臓は中医学の『肝(かん)』と呼ばれる五臓の1つです。日常で感じるストレスとの関係が深い内臓と中医学では考えます。怒りっぽくなったり、過度にイライラしていることにふと気づくことはありませんか?筋肉に現れる場合もあり、こわばり・しびれ・つっぱる痛みとして感じるとのこと。目に感じる不調も『肝』とかかわりがあります。
″HOほ″2023.2月号にて飲食物の「四気五味(しきごみ)」とは?
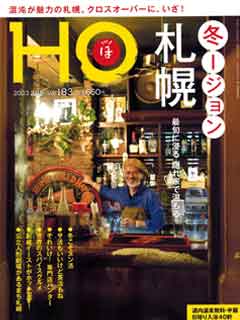
街の身近な健康相談vol.15 「実は漢方薬は料理人が作ったんですよ」と驚くようなお話が載っている今号。「食養生」や「健康」の本質について分かりやすく紹介されています。
″HOほ″2023.1月号にて余分な水や脂肪が体にたまった状態の「痰湿(たんしつ)」とは?
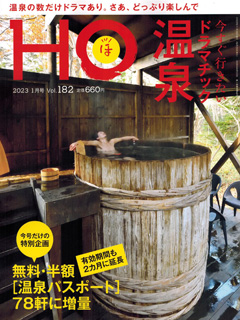
街の身近な健康相談vol.14 体の新陳代謝を活発にするために“水”を積極的に飲むという方法があります。また、お悩みの症状として体や頭、胃が重いと相談に来られる方がいます。この2つは関係があると考えることが出来るのが中医学の考え方です。飲んだ水が処理できずにたまり、それが蓄積していくと「痰湿(たんしつ)」というものに変わると考えます。
″HOほ″2022.12月号にてパーツではなく「全体像」として人間を見るお話

街の身近な健康相談vol.13 中医学の大きな特徴は、人体を1つのつながりとして、細分化せずに全体像を見ることにあります。また人間も自然界の一部と考えるため、自然の動き(気候の変化や自然災害)に影響された時、体調の変化として表れることがあります。
″HOほ″2022.11月号にて日常生活と食の養生で「血・気」の巡りを改善
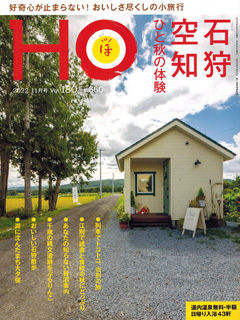
街の身近な健康相談vol.12 肌の黒ずみや乾燥、体の同じ部位に繰り返し現れる痛み、しこりがあると『血瘀(けつお)』という体質になっていることが考えられます。『血瘀』とは「血(けつ)」の運行が滞った状態と考え、『血瘀』が起きると将来のさまざまな病気のもとになる可能性もあるとのこと。養生法をご紹介。

街の身近な健康相談vol.11 強い不安感やイライラ感、不眠にお悩みの方に生活習慣や食習慣を伺っていくと『気滞(きたい)』という体質が見えてくる場合が少なくないとのこと。気の流れが滞った状態の『気滞』体質になると頭痛が起きやすくなることも。女性の場合、生理不順や生理痛にも関係するため注意が必要です。
″HOほ″2022.9月号にて目・肌・口の乾燥が気になる方へ薬膳レシピ2品をご紹介
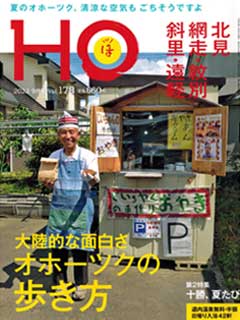
街の身近な健康相談vol.10 中医学ではからだの中の体液成分が減ること(一時的もしくは慢性的に)により、身体の中の潤いが不足するため、目・肌・口に強い乾燥感が現れると考えます。今号では体質名『陰虚(いんきょ)』について、薬膳レシピとともにご紹介しております。
″HOほ″2022.8月号にて赤と黒色の食材で血(けつ)の働きを元気にするをテーマに掲載

街の身近な健康相談vol.9 中医学で考える“血(けつ)”が少ないと、血虚(けっきょ)と呼ばれる体質になり、からだの広い範囲(肌や髪の不調、心や睡眠の不調等)で不調が出ます。血虚体質改善のために食事の摂り方、食材の選び方は夏を元気に乗り切る予防にもなることをご紹介しております。
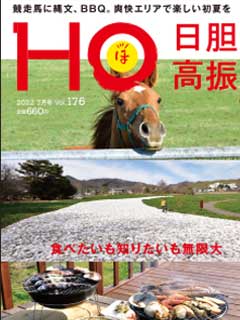
街の身近な健康相談vol.8 少しずつコロナ禍前の日常やイベントが戻り始めている中で、私達は新たなストレスを日々感じて生活しています。中医学では“気(き)”は体を構成する要素の1つであり、気は活力の元と考えます。生活の中で“気遣い”や“気配り”が多過ぎると“気”は減ってしまいます。“気”を減らさないためにはどんな心がけが大切か、どんな食材や生薬が予防になるかを紹介しています。
“HOほ”2022.2月号にて続いているコロナ禍で心の健康を保つ方法についてご紹介
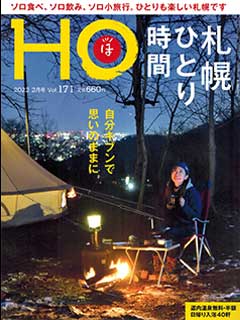
vol.7 気持ちや体調に不調が感じられた時、原因が分からず悩まれている方が増えています。“人を診て病を診る”“心の健康は体の健康から”と考える中医学では、ご相談に来られたお客様の全身の不調に対応できます。日常できる養生法も紹介しています。
“HOほ”2022.1月号にて「つらい冷え」に悩む方へのアドバイスを掲載
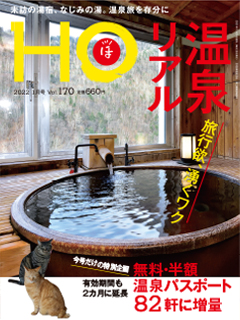
vol.6 感染予防もあり例年より運動不足のままにこの冬を迎えた方は「冷え」を以前より感じやすくなっていませんか?
中医学で考えられる2つのタイプ「冷え性」を養生法とともに説明しています。

vol.5 「疲れ=疲労倦怠感」はどんな病気にも起こり得ます。
病気でもなく、体を過度に動かさなくても疲れを辛く感じることもあります。
西洋医学にはない『気(き)』・『虚証(きょしょう)』という中医学的考え方から原因や改善策を提案しています。

vol.4 秋は肺の季節ととらえ、皮膚とも関係すると中医学では考えます。
長引くマスク生活で本来の肺呼吸が難しいところに夏の猛暑の疲れも加わり、肌の不調や秋バテになっていないか注意が必要です。
手当法、食事法のアドバイスも提案しています。
ご相談予約プレゼントも実施中です。
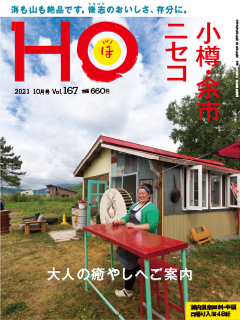
vol.3 デリケートな悩みである「抜け毛」について。
皮膚疾患と内臓のバランスから原因を考えることができる中医学的考え方を説明。
ご相談予約プレゼントも実施中です。
北海道総合情報誌"HOほ”にて『街の身近な健康相談』と題した連載スタート
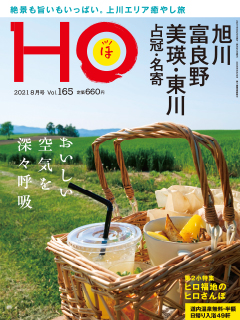
vol.1は全道各地47店で作る北海道中医薬研究会の成り立ちについて。
漢方専門店での健康相談とは?現代の生活に合わせて作られた中成薬(漢方薬)があることなど掲載。
ご相談予約プレゼント実施中。
![北海道情報誌HO[ほ]に掲載されました](images/bn_media_ho.png)